昨日の話…地元の桶川市歴史民俗資料館に顔を出してみたら、明日からの企画展のために準備中という札がかかっていたので、
それなら、明日来てみようとなり、連日の訪問となった。

ここ、看板のとおりで、裏には今年オープンした「道の駅」がある。
だが、れっきとした別の施設。
今回の企画展示は「駅できた、街できたー中山道の驛から鉄道の駅へ」というもので、JR桶川駅が開業140年を迎えたことから企画されたそうだ。
展示スペースは資料館の奥のスペースで、江戸時代の桶川宿の役割から、現代の桶川駅までの内容が駆け足だけど、密度濃いめで紹介されている。

桶川駅の利用目的は貨物が主流だった!?
今でこそ、郊外のベッドタウンという感じがする桶川駅ですが、
日本鉄道会社が桶川駅を開業したとき、その主目的は「貨物」。
中でも、多かったのが「甘藷」つまり、サツマイモでした。
サツマイモって言うたら、埼玉県人でも川越の方をイメージします。実際「栗より美味い十三里」と称されたのは川越ですし。
だけど、幕末~明治期だと桶川を含む北足立郡が県内トップの生産量を誇ったらしい。
儲かる所にはトラブルあり、で1860(万延元)年と、1867(慶応3)年には、
鴻巣の八百屋集団は、利益を独占しようと産地の囲い込みをたくらみ、
桶川の農家は相場より安く買いたたかれるのはガマンならん!と
訴えバッチバチの争いを起こしたそうです。
結局、この囲い込みは失敗に終わって、自由な売買が維持できたらしい。
さらに、1897(明治30)年10月には芋がらみでもう一つトラブルが。
日本鉄道が、貨物車両の手配を忘れて、桶川駅が芋だらけ!
奥羽地方に向けて出荷する貨物車両60両分のサツマイモが取り残され、そのまま腐ってしまった、というのです。
これで大損した、商人も農家も大激怒…その後、どうなったのか、気になったのですが
なんと、その後の話は不明…というから、ビックリ。
当時の新聞を探したら、ニュースが載ってそうなもんですが…
東京から疎開が来る場所だったんか!?
住めば都とはよく言ったもんで、自分の住んでる場所が田舎だとは全然感じませんが
これが明治期だったら、上記のように、イモが似合うのどかな農村だった桶川。
これが、徐々に乗客が増えていきました。
太平洋戦争の際には、集合場所が桶川駅だったこともあって、徴兵された人がのぼりを立てて行列をなしたそう。
また、戦争末期には東京の保育園生が疎開のため
桶川駅に降り立ち、市内の知足院や、7キロ離れた蓮田市の妙楽寺まで歩いて行ったと言います。
それをもとに小説も書かれ、映画化もされているとか。
桶川が映画…不思議な気分です。
戦争中に工場も移転、そっから都市化、現代へ。
疎開してきたのは、保育園だけじゃなく、戦争のはじまる1940(昭和15)年の三井精機工業を皮切りに、今の三菱マテリアル、
戦後には三共理化学などの工場がやってきます。
工場ができれば、職場に通う人が家を構える。
戦後はこの人たちが桶川周辺で家を構えるし、都内で働いている人も宅地を求めて移り住むようになります。
三井精機がさらに別の場所に移転となると、跡地に若宮団地が建設されたり
桶川マインができたりする。
桶川マインは1988(昭和63)年開業で、4階建ての地元じゃめずらしい大型店舗。
当時隣の北本市に住んでいましたが、自転車を飛ばしてプラモやカードダスを買いに行ってたもんです。
屋上に遊戯施設が充実してたり、映画館もあったですよ。
湘南新宿ラインや上野東京ラインなども開通し、池袋、新宿方面や、上野より先にも一本で行けるようになったものの
このあたりは、他に路線が育たず、結果…
高崎線一本足打法なんで、どっかが止まれば即座に遅延、という脆弱性(陸の孤島、と資料では解説がありましたが、まさにその通り)が課題になってる、とのこと。
知ってること、知らないこと様々ですが、こう見ると結構面白い。
人のいるところ、歴史があるもんだとしみじみ思います。
最後まで読んでいただきありがとうございます。ブログ主のモチベーションになりますんで、この記事が面白かったらTwitterリツイートやシェアボタンで拡散、よろしくお願いいたします。
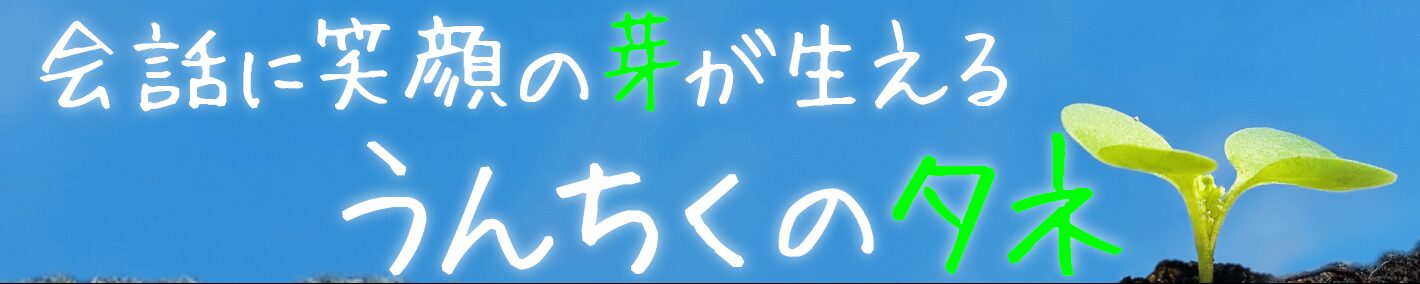



コメント