最近、kindle には助けられている。かつてだったら幻の著作と呼ばれたものも
様々な形で電子化されて、気軽に読むことが出来るのだから。
現在、主に読んでいるのは9歳で明治天皇に仕えたのを皮切りに、大正天皇、秩父宮雍仁殿下、貞明皇后に仕えた坊城俊良(としなが)さんの「宮中五十年」。

以前紹介した「明治宮殿のさんざめき」の紹介記事で昔の本を読む難しさをちょろっと書いた。
彼らのいる世界がブログ主の生きる世界と違い過ぎて、解説が必要なところが多々あるからだ。
この本も初めて出版されたのが1960(昭和35)年であり、晩年を迎えた著者が振り返るという内容で、そのような読みにくさがあるのではないか、とおもっていたが
本書は極めて読みやすく、おそばにいた人間ならではの天皇、皇后、そして、皇族の人間模様が分かって非常に面白い。
筆者のキャリアは1902(明治35)年に明治天皇に出仕したことから始まる。
筆者の明治天皇へのイメージは「慈父」だと私は思っていて
一度言いつけられたことは二度と言わない、という厳しさを持ちながら、とても思いやりが深く、小さなことにお気づきになった、と振り返る。
筆者の体格が貧弱だと気付くと、ご馳走をしてくれたり、新宿御苑でとれたジャガイモを下賜されたりした、とのこと。
また、すべてがキチンと整理されており、モノを取りにやらせるときも、細かな場所までしていして指示を出し、それがまたその通りの場所に収まっているなど、几帳面な一面も見せている。
明治天皇のエピソードでも紹介した「雪の日に雪山をつくる一日」を体験したひとりがこの坊城さんであり、心の底から敬慕されている様子がうかがえる。
また、昭憲皇太后は身体が弱く、しばしば御用邸に子どもたちを招いて、かるたをしたり、おやつをもらい、一日遊ばせていた子ども好きなエピソードを紹介しつつ、
学問が出来なければいけません、と綴方(作文)を課したり、仕事で学習院に通えないかわりに英語や漢文の試験を行ったりしていた、という話も出てくる。
仕事をしているが、ホント親代わりなんである。
そんな感じで、仕えた人の思い出が書かれている。これは公式ではない、表に出ない話ばかりなのでとても読んでいて楽しい。
まだ、大正天皇の思い出に入ったばかりだけど、とても気さくで、自由を愛する優しい人柄をうかがわせるエピソードも非常に面白く、読むのにまったく骨が折れない。
また、歴代の陛下がかわれていたペットの話も面白い。
明治天皇の犬は、陛下が執務室にいるときは威張っているけど、いなくなると途端にかわいくなる、と言った話や
大正天皇の飼っていた九官鳥が、陛下のマネをして坊城さんを呼ぶので、つい騙されて執務室にくる話を面白がった新聞社が記事にしちゃった話には、
筆者を気の毒に思いつつも、思わずクスリ、としてしまった。
面白いのは、1946(昭和21)年の正月1日に掲載された「人間宣言」についての感想もチラリと触れていたことだ。
短いながらも仕事でつかえた人々をどう感じていたかが、はっきりわかるのが印象的だ
終戦後、占領政策の要請とかで、わざわざ〝人間天皇〟の御宣言があったが、私たちからいわせると、不思議でもあれば不可解でもある。
(p.59)
こうやっておそばで天皇や皇后、皇族方に直に接している筆者にとっては、紛れもない人間であり、神様なんかじゃない、ということである。
一般の人にうかがい知ることのできなかった皇室、皇族の人々をつぶさに目の当たりにして
本書で時に厳しく、時に優しい、お茶目でもある歴代陛下や皇后、皇族の思い出を披露しているのは
筆者が、そのことを伝え、後世まで語り継いでほしいという願いがこもっているように、ブログ主には思えてならないのである。
【関連記事】

最後まで読んでいただきありがとうございます。ブログ主のモチベーションになりますんで、この記事が面白かったらTwitterリツイートやシェアボタンで拡散、よろしくお願いいたします。
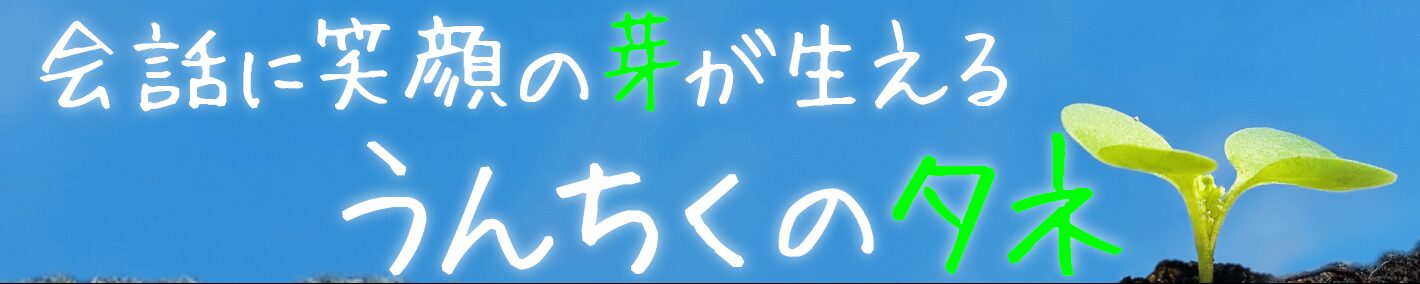



コメント