忙しい時ほど、読書がはかどる…とはよく言ったもので
仕事をやめて時間が出来ても、読書がすすまなかったのに、毎日朝から夕方まで勉強していると不思議と本が恋しくなります。
htmlだ、cssだ、いや、Photoshopだofficeだと頭に叩き込みながらも
この本が実に面白くて、休み時間や昼ご飯の時にも読み進め、あっという間に読了しました。

三遊亭好楽師匠、というと笑点のピンクのスポ刈り…と言うイメージで、番組内だとド派手な感じがなくて
赤字続きの「しのぶ亭」を経営するビンボー人キャラ…という感じですが
…おみそれいたしました。
本を読んでいて、色んな師匠方との濃ゆいお付き合いがあって、こんな裏話を本一冊書けちゃう人だったとは。
好楽師匠の最初のお師匠さん、林家彦六師匠は当然として
桂文楽、古今亭今輔、林家三平、立川談志、古今亭志ん朝、春風亭柳朝…と昭和の落語家のビッグネームがずらずらずらっと。
しかも!ご本人が目撃した話で、初めて聞くような話もいっぱいで、ページを繰る手を止められませんでした。
入門の時のエピソードがいきなり面白い
なかでも、一番強烈なのが「最初の師匠」林家彦六師匠の話。
三国志の劉備は諸葛孔明を口説き落とすのに「三顧の礼」をした、と言いますが当時の家入信夫少年は4回足を運んだと言います。
最初彦六師匠は70過ぎたから弟子は取らない、と言っていたのですが、3回目に信夫という好楽師匠の本名を知って、
「ばあさんや、『のぶお』が帰って来たよ」とひと言。死んだ息子と名前が同じだから入門を許可した、とのこと。
それで「明日お母さんを連れておいで」と言われて、母親同伴で師匠にご挨拶。
「こんな子をこんな世界に入れちゃっていいんですか」と師匠がお母さんに尋ねると
「泥棒よりはいいと思います」とお母さん。
これには師匠も思わず大笑いして、入門が決まったエピソードは、落語みたいで傑作です。
まぁ、その後23回「破門だぁ」となるんですが…。
あ、池袋の一列目じゃねぇか!?
昭和最後の大名人候補、古今亭志ん朝さんとのエピソードも面白い。
高校生時代、毎日池袋の寄席に通って最前列で落語を聞きに行ってた好楽さん
彦六師匠に弟子入りして、古今亭志ん朝師匠に挨拶したら、顔をマジマジと見て
「あ、池袋の一列目じゃねーか」と言われた後
「お前が毎日来るから、ネタを変えなきゃいけなくて苦労したんだぞ」と文句を言われたそうで。
たしか落語は10日に落語家さんが入れ替わるから、10日連続で来たら、日替わりなら10演目…
まぁ、確かに大変ですね。
でも、先頭に座っているとはいえ、高校生のガキ(失礼)のために「コイツを満足させてやる」と考えていたんでしょうね。
で、志ん朝師匠だから、トリ(最後に上がる人)でしょうし。余計ですよね。
なんか、芸もリズムよく、格調よくタタタターンと畳みかける話術が魅力的だった
志ん朝師匠らしい、すごく生真面目なエピソードで、私は好きです。
気難しい人に見えた談志師匠の真っすぐな心意気に脱帽!
この本で一番好きなのは、やっぱり立川談志師匠のエピソードです。
東京都荒川区のムーブ町屋のこけら落としに立川談志師匠が登場した時
客席には、余命いくばくもない患者と付き添いの医師、看護婦の3人組が。
ベッドに寝た切りで点滴を付けたままの姿で「談志の落語を聞きたい」とやって来たといいます。
「どうしたものか」と主催者が困惑していると、
普段から談志師匠にかわいがられていて、この日の出演を控えていた好楽師匠が通りかかり
「一番前で見せてあげればいいよ。談志師匠?怒らないよ」と進言したそうです。
…で、談志師匠の出番になり、
お辞儀を済まして「えーっ…」っと客席を見ると、その患者が目に留まった。
談志師匠、怒るどころか3人を見てすぐ察して
「いいカタチだね。そうか…死ぬ前に俺の落語を聞いてあちらへいこうという、そういうオツな考えで来たんだね。先生たちもご苦労さん」
まずは客席がどかーん、と沸いたそうです。
そして「冥土の土産にとびきりのを持ってけ!!」と言わんばかりにこの日の談志師匠は冴えに冴えて
患者さんも手を叩きながら大笑いして帰って行った…
私、談志師匠というと生前の奇人ぶりが目に焼き付いちゃっているんですが、
周りにいる人のエピソードを読むと、照れ隠しで変なことをするけれど
実に繊細で、心のまっすぐなところを持ってる気がします。
きっと、落語家冥利に尽きる、と言う思いで渾身の一席をやったんだろうな、と感じました。
昭和の落語ファンには、面白い話いっぱいありますから、ぜひ読んでみてください。
これはおススメですね。
最後まで読んでいただきありがとうございます。ブログ主のモチベーションになりますんで、この記事が面白かったらTwitterリツイートやシェアボタンで拡散、よろしくお願いいたします。
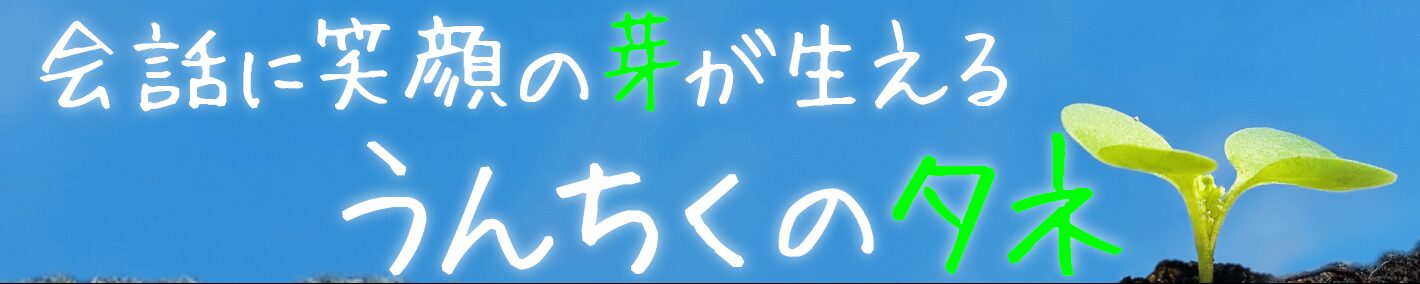



コメント