この記事では、岩井秀一郎さんの『渡辺錠太郎伝』を読んで、感想を書いていきます。

私自身、渡辺錠太郎というと「2・26事件で殺害された人」以上の知識を持っていなかったのですが、この本を読んで、こんな時代を読めるスゴイ人が日本にいたことと、この人が大事な時にいなかった日本の不運を感じた次第です。
小学校から陸軍士官学校へ
実はこの渡辺錠太郎、小学校までしか正規の教育を受けずに、仕事をしながら時間を見つけると同級生のお下がりの教科書を学び、仕事が終わってからも勉強するという猛特訓を積み「仕事をすると頭の冴えが良くなる」と言っていたそうです。
そういった独学で勉強を重ねて陸軍士官学校に入学するという離れ業をやっています。しかも、受験地区ぶっちぎりの一位でです。
陸軍大学校に行ってもさらに勉強を重ね、首席で卒業。
その後、山縣有朋の副官となりここで終生持ち続ける「学び続ける姿勢」を持つことになります。
山縣はとにかく本を読む、ひたすらどん欲に知識を吸収した人物だったそうです。
のみならず部下にも課題の本を読ませて、「重要な点はどこか、なにを知らなかったか」など年中問い詰める人だったらしい。曖昧な答えが返ってくるようなら即座に矢のようなツッコミが入ったとか。
私は本好きだけど、こんな事上司にされたら正直嫌になりますよ。
だけど、渡辺さんの偉いところは「自分を伸ばすのに役立つ」と徹底的に上官の要求にこたえて猛勉強を続けたこと。そして、その働きぶりが認められ、第一次世界大戦のヨーロッパに派遣されます。
第一次世界大戦のヨーロッパを見て、非戦を唱える
そこでは、国家が総力を挙げて戦う当時の戦争を目の当たりにします。
日露戦争までの日本の経験では、戦争は軍人がするものであり、一般人が巻き込まれるなんてなかったものでしたし、第一次世界大戦にも、ほんのちょっと参戦した位なので最新の戦争がどういうモノか、イマイチピンと来ていませんでした。
しかし、時代は銃後の備えとして国民への動員も進むようになり、また飛行機が戦争に投入されることによって一般人への空襲も起こるようになります。
この戦争で敗北したドイツは、皇帝の権威が失墜し、国中が屋台骨を失ってバラバラになり、混乱の極に陥る様を目にします。
そして、何よりも大事なのですが、勝っても負けても働き盛りは戦死したり、負傷で思うように働けなくなったりと、国のダメージが半端ない。
という実情を渡辺さんはつぶさに学ぶわけです。
軍隊は相手に侮られ、付け入れられたらダメなので、システムや装備を総力戦の時代に対応できるようにアップデートさせなければいけない。
同時にそれは戦争を防止するためにするものであって戦争は避けなきゃイカン!と考えるようになります。
これは、同時期にやはりヨーロッパに派遣された永田鉄山も同様の危機感を共有していました。
ただ、永田鉄山はどちらかというとシステム面での総力戦体制構築に意識が行っているとおもいますし、渡辺錠太郎は戦争の惨禍がいかに大きな禍根を残すかに視線が行っていると思います。
殺されたのは、ホント不運
時代を読む目も適切で、軍人は政治に口出しするのではなく、職務に対して忠実でいることが大切。という極めてまっとうで、優れた人物なんですが、
戦前の日本陸軍には「皇道派」が台頭します。これはすごーく乱暴なんで「実業家も政治家もみんな腐ってる!天皇陛下をトップにして軍の独裁を確立しまっとうな政治を目指す!」というちょっと逝っちゃってる連中です
私、皇道派が大嫌いなんで厳しい言い方になるんですが、彼らは公務員なんです。その分際で世直し、下克上を唱えます。
【参考記事】

確かに、当時は今とは比較にならないくらい日本が苦しい時代で、政治家は役立たずってのも分かるっちゃ分かるんだけどね。
でも、そんな寝言をほざく若手を焚きつけて、自分たちの美味しい方向に持っていこうとする将軍なんかもいて、陸軍内は皇道派と、彼らを抑えようとする統制派に真っ二つ。
渡辺錠太郎は「仕事に専念し、軍人は政治だ思想だとみだりに言うもんじゃない」と至極まっとうな主張をし、跳ねっかえりがアブナイことをさせないようにと奮闘するのですが、
そこを逆恨みというかなんというか、2・26で暗殺されてしまうんです。
ちなみに、私は思想信条というよりも、頭に血が上って自分の職場の人間を動員し、斎藤実や高橋是清、そして現役軍人としてはこの渡辺錠太郎を殺害したというのは、
いいも悪いもない、論外なとんでもないことだと思っています。
後に総理大臣となって日本を終戦に導いた鈴木貫太郎さんも殺されかけたし、頭に血が上ると人間ろくでもないことをしでかすというものです。
被害者の家族と加害者の家族が通じ合う、ご縁の不思議
この本の最後では、渡辺錠太郎の末娘で、後に『置かれた場所で咲きなさい』などの著作でも有名になった渡辺和子さんと、

青年将校を兄に持った安田善三郎さんとの交流が描かれます。
キリスト教の洗礼を受け、敵を赦せとの神の教えがあっても、やっぱり憎む気持ちを捨てきれないで苦しむ和子さんと、
2・26で反乱軍として活動、死刑に処せられた兄の罪に対し、贖罪の気持ちを背負いながら常に生きざるをえなかった安田さん
2人は事件から50年後に出会い、そこから人間として付き合うことによって、
和子さんの死まで、深い心の交流を続けることになる不思議を感じます。
もし、あの事件が無かったら、2人とも傷つくこともなかったわけです。ただ、被害者の遺族、加害者の遺族として直面し、交流していくことになったのは、人生というモノのほろ苦さ、不思議さを深く感じるわけです。
この本、ふと思い出して、隣町の図書館から借りてきたんです。借りてきた本だから書き込みもダメですし、汚したりしないように大事に読んでいたのですが、また自分で買って改めて読み直したい。
素晴らしい本だと思います。おススメ!
【関連記事】


【参考文献】
最後まで読んでいただきありがとうございます。ブログ主のモチベーションになりますんで、この記事が面白かったらTwitterリツイートやシェアボタンで拡散、よろしくお願いいたします。
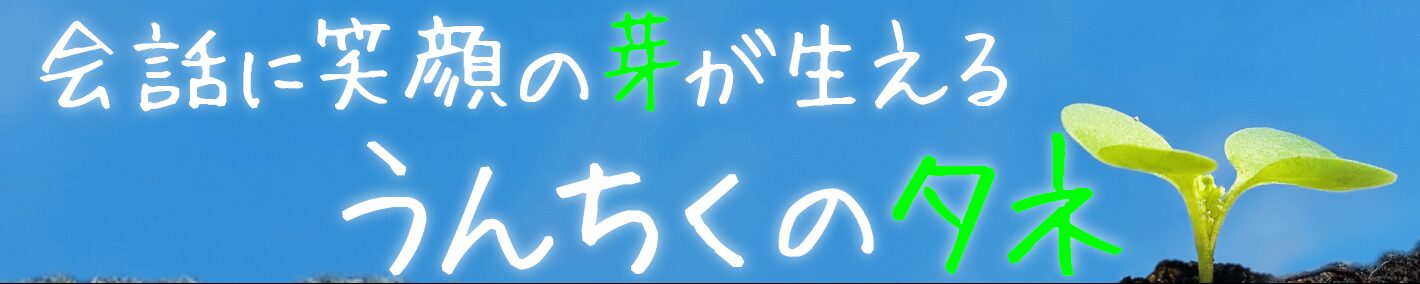



コメント