仕事で本を読む人なら誰でも
「1分でも短く、本の内容を理解できたらいいのに」という願望があるでしょう。
巷には速読法の本も少なくなく、そんな本ばかりか速読法講座とかに大金を投じちゃう人もいるかもしれません。
でも、「ザーッと読めて、全部頭の中に入る」なんてこと、本当に可能なのでしょうか?
この記事ではそこの所を役得のない、一人の本好きとして、考えてみましょう。
速読できる?と聞かれたら…
私は大学時代に「一日一冊」をノルマにしていました。卒業後も最低毎年2、30冊は読んでいるので少なくとも2000冊は読んでいることになります。
で、その事を話す時によく聞かれるのが
「ぶっちゃけ、速読できるの?」という話です。
答えは、YES。
ただ、質問者の意図とは、若干意味が違う「速読」ですが。
私の速読は「この本のこの辺に目指す内容がありそうだ」というのを見つけだすことで、
熟読の超スピードバージョンではないんです。
速度と精度はトレードオフ
読み慣れている人は精読の速度を上げることが出来ますが、よくある速読法のように速読して一度にたくさんの情報を瞬時に吸収するというのは、あまり信頼性がないと思います。
本を読む際に速度を取れば、注意深さに欠けてしまうし、注意深く一文一文を読んでいけば、自ずと速さは落ちます。
こういった、「あちらを立てればこちらが立たず」という関係を、トレードオフの関係と言いますが、速読と熟読の関係は間違いなくこれです。
もちろん、例外もあります。サヴァン症候群の人の中には膨大な情報をまとめて処理できる人間がいる、といいます。
こういう人の中には、文章のページを脳みそに焼き付けるように覚える力を持つ人がいて、
博物学者の南方熊楠(1867~1941)は、そういった適性を持っていた一人だといわれています。

南方熊楠がとてつもない記憶力を持っていたのは有名で、子供の頃、立ち読みした『本草綱目』全部(全52巻)を丸暗記して自宅に帰ってから写本を作った、というとんでもない実話があります。
この人はホンモノの知の巨人です。
彼の著作「十二支考」は、古今東西、高尚なものから下ネタまでを縦横無尽に使い、十二支を語りつくすというもので、一読すればその圧倒的な知識量に圧倒されてしまうでしょう。
これは、全員100メートルを9秒台で走れと要求するようなもんで、誰しもが彼のような能力を持つわけでない。
南方の読書は、常人には難しいというほかはありません。
速く本を読める人は、熟読が速い
もちろん、読書のスピードには個人差がありますし、本の分野を熟知していればその分、速く読めるというのは事実です。
特に分野ごとの背景知識は、その人の向き不向きがはっきりしてきます。
私だったら、歴史の本はそんなに意識しなくてもある程度のスピードを出せますよ。
でも科学・技術書の類は予備知識ゼロですから、場合によっては実際にその本通りに手を動かして実物を理解しながらでなければ理解すらおぼつかないですし、読みこなすこともできません。
知らない分野では、入門書やマンガなどの力も借りながら、土台を作った方が早いかもしれません。
しかし、熟読の数をこなすと、個人差はありますが速度は確実に上がっていきます。
背景知識や、語彙などが頭の中にストックされるからです。内容をしっかり読まなければ意味のない小説やルポルタージュなどは、速読で斜め読みする意味があまりないといえるでしょう。
速読は、欲しい場所を探すために使う
では、速読の意味とはどこにあるのでしょうか。
それは、資料として、必要な情報を拾い出すときです。
本に書いてある内容の中から今必要な場所を探したい、記事を書くために付け焼刃でも補助が欲しい
といった用途だと、該当箇所を探し出すために速読は有効です。
私自身、卒論を書く時に内容が「外交や戦争でいかに情報収集するか」だったので、
日露戦争、太平洋戦争、他に他国の例を挙げるために同時代の他国はどのように行っていたか
だけを次々と拾い出していました。それも、出来るだけ多く。
もちろん、該当する場所を見つけたら熟読に切り替えたのは言うまでもありません。
速読の上のテクニック、超速読
これは私はできないのですが、
この世には一冊を10分前後で読み切る『超速読』をできる人もいます。
作家で、元外務省主任分析官の佐藤優氏は、自著「野蛮人のテーブルマナー」でこの超速読を実際にやって見せています。

やり方は…
「呼吸を整え1ページ1ページをめくり、写真を撮るように全体をパッと眺めていく感じ」だそうです。
しかし、このやり方だと、「この本は主人公が女性、舞台は湘南周辺が多く、物語の中心にはお酒がからむケースが多い」という極めて大づかみな情報を得られる程度のようです。
佐藤さんは毎月膨大な量の本を読むことで知られる方ですから、
場合によって熟読、速読、超速読の3種類を絶えず使い分けながら「熟読する本を選ぶ」と話しています。
基本は、熟読
大事なのは熟読して読めない本は、速読しても読めないということです。
ですから、本を読むということは基本熟読であると考えるといいと思います。
最後に言いますが「誰でもあらゆる分野の本一冊を尋常じゃないスピードで読み、内容を詳細までつかむことができる」という速読法なるものがあるとしたら、それはオカルトかインチキでしょう。
騙されないように、ご用心を!!
【この記事が面白かったらコチラもどうぞ】

【参考文献】
最後まで読んでいただきありがとうございます。ブログ主のモチベーションになりますんで、この記事が面白かったらTwitterリツイートやシェアボタンで拡散、よろしくお願いいたします。
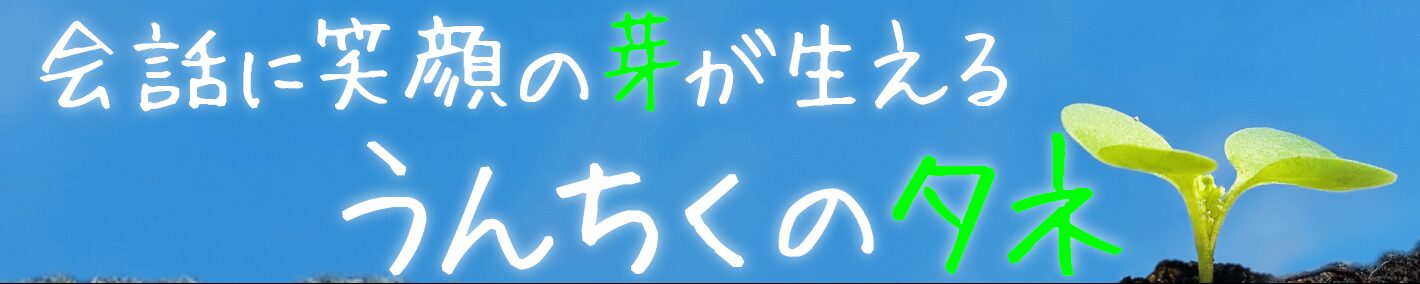



コメント